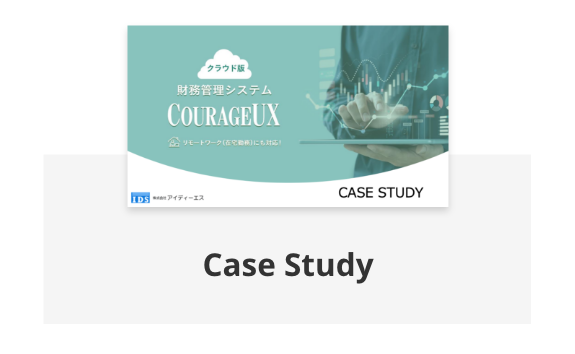webマガジン
Courage Lab
2025.10.30
COURAGEUX
資金調達
ROE(自己資本利益率)とは?資金調達戦略に活かす自己資本利益率について詳しく解説!

はじめに
企業の成長を支えるのは日々の資金調達と財務戦略です。その中で投資家や銀行が注目する指標の一つがROE(自己資本利益率)です。ROEは単なる会計数値ではなく、借入金の水準や資金調達戦略と密接に関わる重要な財務指標です。経営企画や財務・経理担当者、そして経営層にとっても借入金がROEにどう影響するかを理解することは必須です。本記事では、借入金とROEの関係を中心に、実務や戦略判断にどのように活かせるのかを解説します。
ROEとは?借入金との関連性
ROE(Return on Equity/自己資本利益率)は、株主資本を活用してどれだけ利益を生み出したかを示す指標です。計算式は「ROE = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100(%)」となります。投資家はこの指標を通じて企業の収益性を評価しますが、銀行も融資審査でROEを重視します。借入金の返済能力や資金繰りの安定性を見極める際、ROEは必ずチェックされる項目の一つです。
借入金とROEの関係
借入金はROEに直接的な影響を与えます。借入金を増やすと自己資本比率が下がり、レバレッジ効果によってROEが上昇します。ただし借入金が過剰になると金利負担が利益を圧迫し、ROEは低下します。つまり借入金をどう設計するかによってROEは改善も悪化もするのです。
借入金とROEの関係
借入金増加 → 自己資本比率低下 → ROE上昇
過剰借入 → 金利負担増大 → ROE低下
部門別にみる借入金とROEの活用
経営企画部門にとって、借入金とROEの関係を理解することは中期経営計画のKPI設定に役立ちます。資本コストを上回るROEを実現できるかどうかは戦略評価の大きな基準です。
財務部門にとっては、銀行交渉や資金調達の場でROEの改善を示すことが借入金の妥当性を説明する有力な材料となります。DSCR(債務返済余裕率)など他の財務指標と併せて提示することで説得力が高まります。
経理部門にとっては、決算や管理会計において借入金残高とROEの変動要因を分析することが求められます。投資家や監査法人への説明責任を果たす上で不可欠です。
経営層にとっては、借入金によるレバレッジ効果とROEの動きを把握することが投資判断やM&Aの意思決定に役立ちます。どの程度の借入金がROEを高めるのかを理解することは経営戦略の実行に直結します。
借入金とROEのシミュレーション
以下は借入金の規模によってROEがどのように変動するかをシミュレーションした例です。
借入金なし:ROE = 10%
借入金5億円:ROE = 15%(利益拡大で改善)
借入金10億円:ROE = 8%(金利負担で逆効果)
この例からも分かるように、借入金はROEを改善する可能性がある一方で、過剰に利用すると逆効果を招きます。資金調達の規模と条件をどう設計するかが極めて重要です。
借入金戦略におけるROE活用の視点
ROEを借入金戦略に活かすためには、三つの視点が求められます。
1. 収益性と安全性の両立
借入金によるROE上昇効果だけでなく、自己資本比率やDSCRなど返済能力を示す指標も併せて確認すること。
2. 短期と中長期のバランス
借入金による一時的なROE改善に満足せず、中期的に持続可能な財務基盤を意識すること。
3. ステークホルダー別の説明力
投資家には資本効率、銀行には返済能力、経営層には戦略実現力としてROEを説明すること。
まとめ
ROEは投資家のための数字にとどまらず、借入金戦略と企業価値を結びつける重要な指標です。経営企画にとっては戦略の評価基準となり、財務部門にとっては資金調達の武器になります。経理部門にとっては説明責任を果たすための指標であり、経営層にとっては株主価値を高めるための判断基準となります。借入金とROEの関係を正しく理解し資金調達に活かすことで、企業は成長と安定を両立させることができます。