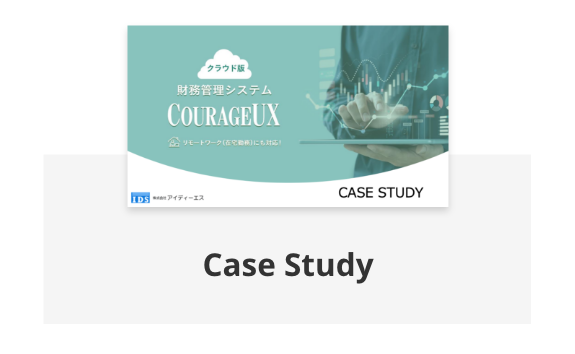webマガジン
Courage Lab
2025.10.15
COURAGEUX
資金調達
負債比率とは?D/E比率との違いを理解して資金調達戦略、借入金管理に活かす!
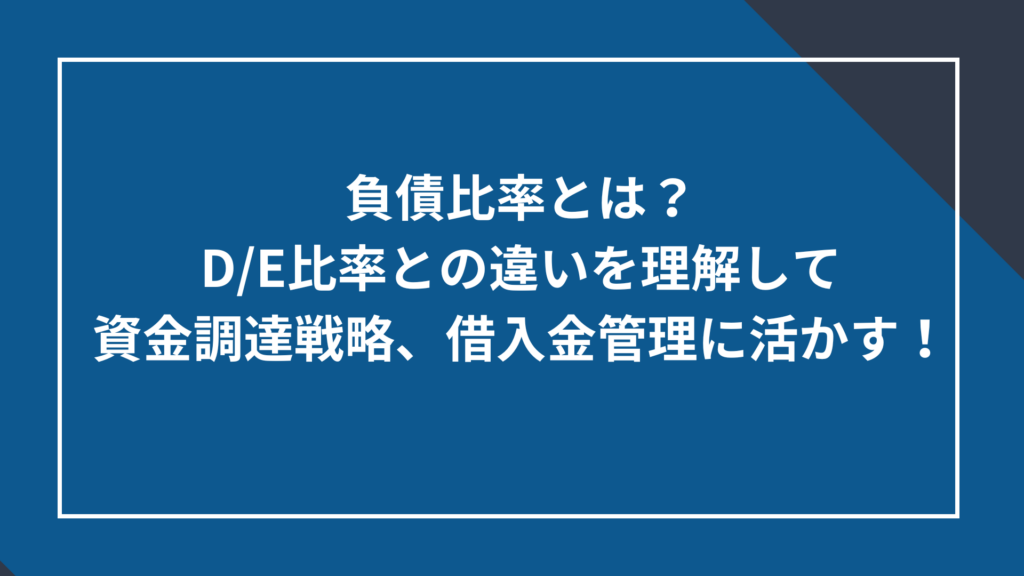
はじめに
経理・財務担当者にとって、企業の財務指標を正しく把握することは、資金繰りや経営判断に直結する重要な役割です。その中でも「負債比率」は、企業がどの程度借入金を利用しているかを示す基本的な指標です。銀行融資の審査や社内の資金調達戦略を考える際に、負債比率は欠かせません。
一方で、似た指標として「D/E比率(Debt to Equity Ratio)」も用いられます。両者の違いを理解して活用することは、資金調達の条件改善や投資家への説明に大きな力を発揮します。
負債比率とは何か
負債比率(Debt Ratio)は、次の式で計算されます。
負債比率 = 負債 ÷ 総資産 × 100(%)
これは総資産に占める負債の割合を示し、企業がどの程度借入金やその他の債務に依存しているかを測るものです。
例:総資産 200億円、負債 120億円 → 負債比率 = 60%
→ この場合、企業の資産の6割が借入金などの負債によって賄われていることになります。
負債比率は財務健全性の基本的なチェック項目であり、金融機関が企業の融資条件を決めるうえで必ず参照する指標です。
D/E比率との違い
D/E比率は次のように計算されます。
D/E比率 = 有利子負債 ÷ 自己資本
つまり、自己資本に対してどれくらい借入金を利用しているかを示す指標です。金融機関や投資家は、レバレッジの強さを確認するためにこの比率を重視します。
比較表
| 指標 | 計算式 | 分母 | 分子 | 主な意味 |
| 負債比率 | 負債 ÷ 総資産 | 総資産 | 負債(有利子+無利子) | 企業全体の安全性を確認 |
| D/E比率 | 有利子負債 ÷ 自己資本 | 自己資本 | 有利子負債 | 借入金に対する資本の健全性を確認 |
- 負債比率:総資産全体に占める負債の割合
- D/E比率:自己資本に対する借入金の依存度
両者を併用することで、財務リスク管理の精度が高まります。
D/E比率の詳細については以下記事をご参照ください
https://www.ids-soft.co.jp/brand/2025/01/28/fundraising-40/
負債比率の活用場面
1. 資金調達戦略の立案
負債比率が高すぎると、銀行は「返済能力に不安あり」と判断し、借入条件が厳しくなります。逆に負債比率が低ければ「財務余力がある」と評価され、有利な資金調達につながります。
また、現在の負債比率の数値は変えることはできませんが、銀行との交渉の中で具体的な数値目標(例:〇〇%以下を目指す)を設定することで、銀行からの評価が変わる可能性があります。
2. 業界平均との比較
業界ごとに負債比率の適正水準は異なります。製造業は設備投資のため借入金依存が大きく、比率も高め。一方、ソフトウェア業は資産が軽く、低水準が一般的です。財務担当者は業界平均を参考に財務戦略を策定する必要があります。
3. 経営層や投資家への説明
経営会議やIR資料において、負債比率は直感的に理解されやすい指標です。資金調達計画の妥当性を説明する際、欠かせない項目となります。
負債比率を下げるための実務的アプローチ
① 内部留保を増やす
利益剰余金を積み上げることで自己資本を増加させ、結果的に負債比率を下げることができます。
② 借入金の返済・借り換え
資金繰りに余裕がある場合は、短期借入金の返済や長期借入金への借り換えを進めることが有効です。銀行交渉によって条件を改善できれば、資金調達コストを抑えられます。
③ 資本性調達の活用
劣後ローンやエクイティファイナンスなど、自己資本とみなされやすい調達方法を活用すれば、見かけの負債比率を下げつつ資金調達力を強化できます。
D/E比率との併用が重要
負債比率が低くても、D/E比率が高ければ「借入金が資本に比べて過大」というリスクが残ります。逆もまた同様です。
両者をバランスよく利用し、銀行や格付機関に対して企業の財務健全性を多角的に説明することが、資金調達交渉において極めて有効です。
まとめ
- 負債比率は総資産に対する負債の割合を測る安全性指標。
- D/E比率は自己資本に対する借入金の依存度を示すレバレッジ指標。
- どちらも財務分析・資金調達戦略に不可欠であり、組み合わせて使うことで企業の信用力を高められる。
経理・財務担当者は、これらの指標を適切に活用し、銀行との交渉や経営層への提案に役立てることで、より良い資金調達条件の獲得につなげることができます。