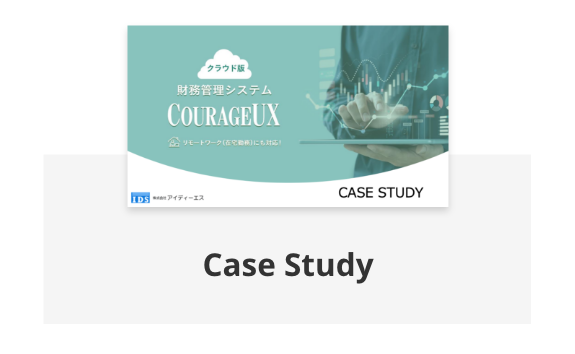webマガジン
Courage Lab
2024.6.5
COURAGEUX
会計
資金繰りのベストプラクティスを見つけるには?実務に即してわかりやすく解説!⑤
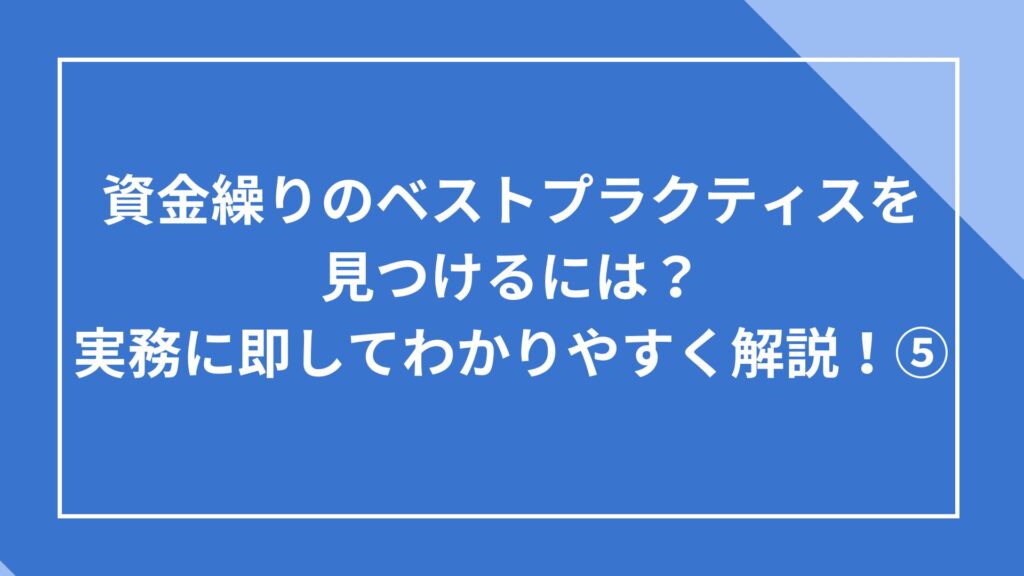
資金繰り業務を成功に導くための記事もついに最終回です。過去4回の記事を復習した上で読んで下さい。
今までの記事では主に資金繰りを成功させるための「前提条件」に重きを置きました。どんなにエクセルの機能をうまく駆使して、素晴らしい資金繰り表を作成してもそもそも前提条件を満たされていない会社では絵に描いた餅になりがちです。そういった企業をたくさん見てきた経験から今回の記事を書こうと思いました。
最終回をむかえて、ついに資金繰り表の話に触れてみたいと思います。たぶん「資金繰り」というキーワードで検索すると最初からこのテーマに触れる記事が多いように感じました。そのアプローチ方法がいけないわけではありませんが、前述したような理由からあえて最終回記事で触れることにしました。
資金繰り表のイメージ
法律で作成が義務付けられているものではないため、絶対にこれじゃなきゃいけないということはありません。しかしそれだと話が前に進まないので一般論としての資金繰り表イメージを下記に載せてみます。

勘の良い方ならピンときたと思いますが、キャッシュフロー計算書に少し似ております。「営業活動」「投資活動」「財務活動」の3つの視点でお金の収支をみるという意味だとコンセプトはとても似ています。
このキャッシュフロー計算書的な資金繰り表が私個人的には好みです。営業活動で得たキャッシュと銀行借入で得たキャッシュの区分けができたほうがよいのは明らかでしょう。個人の財布で考えるとさらにわかりやすいです。今月の出費が給与の手取り額を上回って月次の家計簿がマイナス5万円になってしまった。しかし消費者金融で10万円借入を行い資金収支的には結果的にプラスになった・・・プラスだから大丈夫なんて人がいたら危機感を持たせたくなりますよね。生活収支(給与手取り額-生活支出)と財務収支(消費者金融)がパッと見、区分けされていれば下記のような意思決定や目標が立てれます。
■生活収支がマイナスになっていることに対するチェックポイント
・給与額は適正か
・今働いている会社で給与アップが見込めなければ副業や転職を検討
・来年以降のベースアップや昇給をシミュレーションしてみる
・無駄な出費はないか
・食費が増大していれば自炊をしてコストカット
・安価な代替品で我慢できないか
・使っていないサブスクサービスの解約
→幽霊会員状態のスポーツジムの会費
■財務収支のポイント
・ちゃんと借りたお金を利息含めて期限返済できるのか
・あといくらまで追加で借りることが可能か
こんな感じで「お金に困っている人」や「自分がお金に困っている状態」を思い浮かべてみると、資金繰りはすごい理解が深まります。マクロ視点でまずは「営業」「投資」「財務」の収支をみたあとに、ミクロ視点で細かい支出(先ほどの例で言うと無駄遣いしている経費)に注目して意思決定をするはずです。手元にお金が少なくなれば、一度はこんなイメージで資金繰り予測をしたことが誰にでもあるのではないでしょうか。企業も専門用語がたくさん出てくるだけで、基本的には同じです。
他の点にも軽く触れていきましょう。確定した月と予測の月がわかるように実績月と予測月をわかりやすくする工夫して表示するケースが多いように思います。
経費欄については、人件費以外は詳細名称にはしませんでしたが、細かい出費等は「小口出費」みたいにまとめてしまったほうが良いかもしれません。会計システムの勘定科目ベースならまだしも、補助科目ベースで細かく作成しようとする方がいらっしゃいますがあまり細かすぎるととても見辛くなります。重要性が高い部分については逆に補助科目レベルまで落とし込んでも良いかもしれません。
財務収支については「長期借入金」「短期借入金」といった勘定科目レベルの例にしましたが、銀行ごとにしてみるというアイデアもあります。ほとんど会社で補助科目として銀行の管理を行っているケースが多いと思います。ここは補助科目レベルの管理がマッチする可能性が高いです。
絵に描いた餅にならないために
この章は今までの記事の総復習です。まずは資金繰り表を作成してみましょう。その上で適正な意思決定に役立っているのか?実績値と予測値の乖離が大きすぎないか?等を検討してみて下さい。乖離が大きすぎるとそれは企業実態を表現できているとは言えません。
最初の記事で触れましたが受注予測などの「不確実性」をある程度のレベルでコントロールできているのか、また資金収支の発生場面を全て網羅できているのかといった「網羅性」の2つのポイントを見直して下さい。圧倒的にここが弱いケースが多く見受けられます。この2つを改善すれば問題ないのですが、おそらくそんな簡単な問題ではありません。問題解決するための人材がそもそもいないというところにたどり着きます・・・。(前回記事の内容です)
終わりに
資金繰りのベストプラクティスというテーマで全5回にわたり記事を書かせて頂きました。結論から言うと全ての企業に当てはまる特効薬的な情報はお届けできなかったかもしれません。しかし資金繰り実務の難しさや、なぜ失敗に終わることが多いのか、というところが理解できていればいくらでも対策は立てられるはずです。なかなかこういう視点で書かれている記事が少ないと思いますので、ぜひ参考にして頂ければ幸いです。