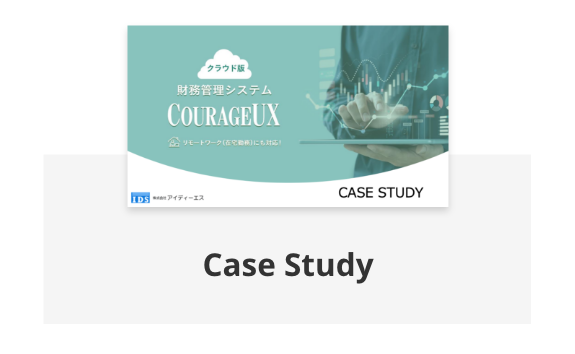webマガジン
Courage Lab
2024.5.29
COURAGEUX
資金調達
会計
資金繰りのベストプラクティスを見つけるには?実務に即してわかりやすく解説!④
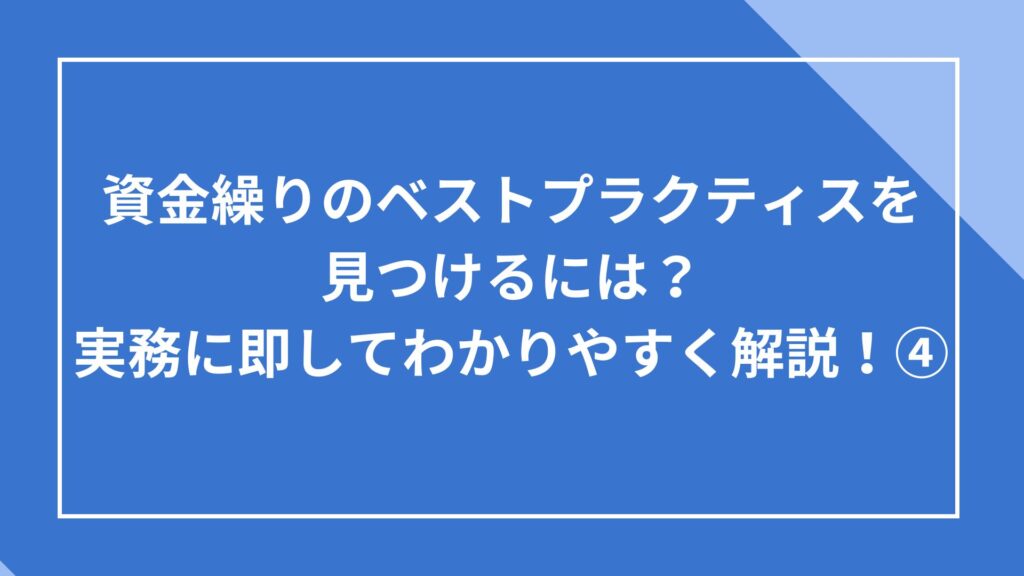
資金繰り業務を成功に導くための記事も第4回目を迎えました。ここでは人材面から語ってみたいと思っております。前回までの記事を読んでまずは復習して下さい。
今まで3回の記事でも触れましたが、資金繰りを成功に導くためにはポイントがたくさんあり、会社全体をマクロな目線でみれる人材が必要不可欠になります。立場は様々で、ある会社では経営者がその役割を担い、一方ではシステムエンジニアや経理/財務担当者のこともあります。またミクロ目線でみれるスペシャリスト的な実務担当者の存在も欠かすことができません。
いずれにしてもそういう人材が存在しない会社では、失敗に終わることも少なくありません。ここらへんが資金繰り業務が上手く軌道に乗せることができないハードルになっているのではないでしょうか。
人材の学習や成長といったポイントは資金繰りの分野で重要な成功要因になると私は考えています。この視点から今回の記事は書かせて頂きます。
簿記は社会人必須スキル
結論から最初に言ってしまうと「簿記の知識」はとても役に立ちます。経営者、経理部や財務部で働く社員に限りません。この分野のメリットは資格検定試験が充実しており、習得するためのカリキュラムが世の中に溢れていることです。したがって本気になれば誰でも知識として身に着けることが可能です。書籍も充実しているため、根気強い人なら独学でも十分な知識を習得できます。全社員に資格取得を推奨すべきと私は思っています。
資金繰り業務と簿記検定はもちろん直接的な関係はありません。簿記検定で資金繰り表の作成等は求められることは無いです。しかし簿記を通して色々な企業実務の場面を簡易的ではありますが体系的に学習できます。さらに「仕訳」という概念を会得することで資金増減の関わる場面が自然と理解できます。「減価償却費の計上」では資金移動を伴わないと言われても簿記の知識がない人には理解できないでしょうが、簿記を少しかじったことのある人からすると、超常識な話です。売上したお金を手形や電子記録債権で回収する場合はそれらの期日ベースで資金予測をたてなければならないことも簿記を勉強している人なら自然と理解できているはずです。
ここらへんは経理部や財務部と働いている人からすると当たり前すぎる知識ですので、この部分は問題ないでしょう。しかし以前の記事でも取り上げた通り営業部の受注報告が資金繰り上の大切な指標になる場面は決して少なくありません。この点はなかなか経理寄りの人材が管理できる範疇にないケースがほとんどです。部署間の横連携が必要になり、その懸け橋になる人材が求められるのです。
会社の組織構成によって若干の違いはあるものの、情報システム部門のシステムエンジニア等にその役割が回ってくることがよくあります。ITやDXという言葉が当たり前になった昨今、資金繰りとシステム化は絶対に切り離すことができません。その調整役を担うのに簿記の知識は最大限に効力を発揮するでしょう。システム部門にはネットワークやセキュリティのエキスパート人材はわりと多くみられますが、意外と簿記/会計に精通した人材というのは少なかったりします。会社間で横展開できるように色々な部署に簿記/会計の知識もった人材を配置することは強固な組織作りには欠かせません。そういう人材を常に育てることができる土壌を作りあげましょう。
キャッシュフロー計算書と資金繰りの違い
簿記を勉強して資格検定に合格した人であれば、財務会計をテーマに書かれた書籍も読めるようになっていると思います。そこにはキャッシュフロー計算書という決算書が紹介されているはずです。お金の出入りを示す書類という点では資金繰りの業務と共通しています。
どんな点が共通していて、どういった点で異なるのか説明してみたいです。簡単に言うと、どのステークホルダー(利害関係者)向けに作成されるかといった箇所が異なります。整理してみました。
・キャッシュフロー計算書
→外部のステークホルダー向け(投資家等)
上場会社等の大企業は法律で作成されることが義務付けられています
過去の資金の流れを実績として公開します
・資金繰り業務で作成する書類
→内部のステークホルダー向け(企業内の意思決定等に役立てます)
未来の資金予測という不確実性を盛り込んで作成するため日々状況が変動します
上記のようになり、基本的には外部ステークホルダー向けと内部ステークホルダー向けと覚えておくと頭の整理がしやすいです。もちろん例外はあります。例えば資金繰りの予測数値等は銀行から融資を引き出す際の交渉材料に使えることもありますので、一部の外部ステークホルダーに公開することはあり得ます。ただしキャッシュフロー計算書のようにインターネットで簡単に検索できるような公開情報ではありません。
キャッシュフロー計算書も直接的に資金繰り業務に結び付くわけではありませんが、やはり考え方はとても有益です。資金の出入りを可視化するという意味では全く同じです。キャッシュフロー計算書では企業の資金移動の活動を「営業活動」「投資活動」「財務活動」という3カテゴリにわけて表現します。「営業活動」は売上/仕入によるお金の移動、「投資活動」は設備投資等によるお金の移動、「財務活動」には銀行からの借入や返済といったお金の移動が表現されています。やはり資金繰り業務についてもどういった活動でお金の動きがもたらされたのか可視化できるように、活動別にお金に色付けしておくとよいでしょう。資金繰り業務を成功に導くためには、損益計算書や貸借対照表だけはなくキャッシュフロー計算書の概念まで頭にいれておくのをお薦めします。
キャッシュフロー計算書はとても奥が深いです。単純に資金収支がプラスになっていればよいという問題でもありません。その企業の成長力やビジネスモデルによって読み方が変わります。営業活動で得た資金よりも投資活動で出て行った資金が上回っていれば、一見すると手元資金が失われているためネガティブな印象を受けます。ただし工場増築や機会設備等の投資が将来的な営業キャッシュフロー増大を創出する根拠を示すことができればどうでしょうか?こういった会社は銀行からみると魅力的な融資先になります。したがって自ずと財務活動のキャッシュフローが大きなプラスになるはずです。企業のビジネスや戦略に応じてカテゴリごとの資金状況を未来に渡って予測していきましょう。急成長を遂げている会社の場合は営業で得たキャッシュよりも投資で出て行ったキャッシュのほうが大きいことも珍しくありません。
「ITストラテジスト的人材」の育成
ITストラテジストとは「経営とITと結びつける戦略家」のことで、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)のホームページには下記のような定義がなされています。
===========================
高度IT人材として確立した専門分野をもち、企業の経営戦略に基づいて、ビジネスモデルや企業活動における特定のプロセスについて、情報技術(IT)を活用して事業を改革・高度化・最適化するための基本戦略を策定・提案・推進する者
出典:IPA(独立行政法人情報処理推進機構)
https://www.ipa.go.jp/shiken/kubun/st.html
===========================
期待する業務と役割についても詳細な記述がされています。ちょっと抽象的すぎて読んでも頭に入ってこないかもしれません。とても難しい資格なのでなかなか有資格者にはお目にかかることはできませんが、必ずしも資格合格者に限る必要はありません。ITストラテジスト「的」な視点をもっていれば十分です。
上記のような目線を持っている人材が一人いるだけで、スムーズに事を運ぶことができるはずです。私はシステムベンダー側の立場でお客様に資金繰りシステムの構築提案をしてきましたが、やはりお客様企業にこういった人物がいるだけで話が前に進むのです。
前回の記事でお話したように、理想論だけでは前進できません。全体最適化イメージを頭にイメージしながらも、部分最適化方向にも頭を切り替えることができることが成功への近道になることもあります。背景にある自社の経営戦略を理解して、道標を見失わないようにみんなを最終的に遠回りでも同じベクトルに誘導できる能力をもった人物の存在がとても重要です。これがまさにITストラテジストの役目だと思います。
終わりに(次回展望等)
私はシステムベンダーという立場からお客様の資金繰りシステム構築化のお手伝いを何度も経験してきました。大成功のお客様、思った通りの成果を産み出すことができなかったお客様、どちらもたくさん見てきました。その中で成功企業の共通点を見出していくと、今回ご紹介したような人材がいるかどうかが大きな分かれ道になっていた気がします。
ちなみにITを駆使できる戦略家を自社内に育てることは、前回お話したERPシステムの導入にも応用ができます。複数部門での横展開が必要な場合には必ずこういった人材が大活躍するので資金繰りという範疇以外にも大きなメリットがあるはずです。
次回が「資金繰り」のテーマでお話するのは最後になります。実際に資金繰り表等に触れてみたいと思います。