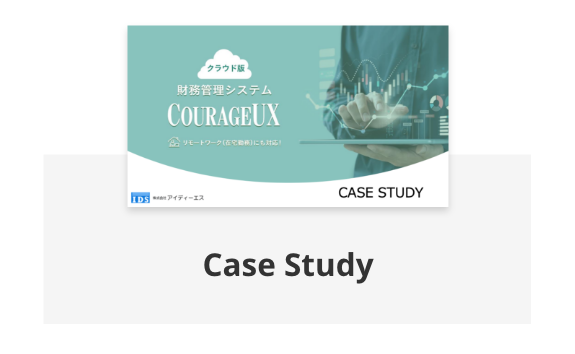webマガジン
Courage Lab
2024.5.16
COURAGEUX
資金調達
資金繰りのベストプラクティスを見つけるには?実務に即してわかりやすく解説!③
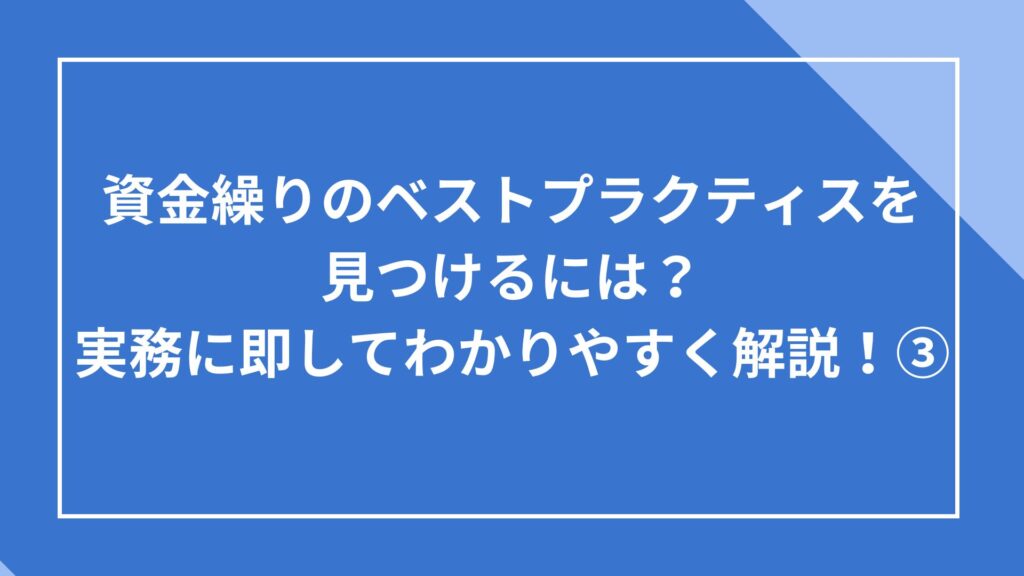
資金繰りについて前2回に渡りお話させて頂きました。そこでは資金繰りが最重要事項であるにも関わらず、多くの企業では理想的な資金繰り管理が行われていないことを説明しました。資金繰りの管理の難しさやシステム化する上でのハードルについて詳細説明をしております。まずは前回の記事を復習してみましょう。
資金繰りを管理する上で何からスタートすればよいのでしょうか。私は数多くのお客様に会計システムや債権債務管理システムを、システム営業/システムエンジニアという立場で提案してきました。そんな私の経験値をもとにした知見の一部を紹介できればと思います。
目次
部分最適化を意識する
私達システムエンジニアがお客様の業務改善のためにお話をさせて頂くときは必ず意識する点があります。お客様企業全体の生産性向上等に貢献ができているかといった視点です。会話をしているご担当者様の仕事は楽になるかもしれないけど、このシステム構築が組織全体で見たときに組織力ダウンにつながるとしたら本末転倒です。こうした企業や組織全体のパワーアップに繋げるアクションを私達はよく「全体最適」なんていう言葉で表現します。対して、特定の個人/組織だけの業務改善にしか繋がっていない場合は「部分最適」という言葉で表現します。お客様企業の「全体最適」にいかに貢献できるかがシステムエンジニアの使命と言えるのです。
資金繰りの管理は過去2回の記事の中でもお話させて頂きましたが、企業のあらゆるお金の動きをトータルで可視化する「全体最適」が求められるエリアというのが簡単に想像できると思います。したがって「部分最適」ではなく、いかに「全体最適」の視点をもてるかが重要な成功要因になるはずです。
しかし表題にもある通り私はあえて「部分最適化」にフォーカスを当てています。失敗例としてよくあるのが「全体最適」の議論をしすぎて、理想論だけが膨らみすぎて結局話が前に進まないという事態です。いきなり全体最適の視点にフォーカスを置き過ぎず、スモールスタートで一部の部分最適から改善してみることが実は近道に繋がることがよくあります。部分最適でもよいからまずはスタートを切ってみる。長い時間をかけて全体最適化に近づけていく、という逆の発想を持っている企業の方が結局のところ成功しているという印象を受けています。
財務周りのお金の動きは確実に見える化しよう
業種に限らずあまり管理内容が変わらない仕事が存在します。それを見極めることがとても重要です。
例えば販売管理の分野等は業種ごとに求められる内容が多岐に渡ります。コンビニエンスストアみたいな小売業と製造業で全く違う管理が求められるのは簡単に想像できると思います。また製造業でも精密機器製造の会社と造船業の会社では全く違うことも、何となく想像ができるはずです。販売予測を資金繰りに利用するのはもちろん大切なのですが、スモールスタートには向かないことも多いでしょう。とても難易度が高いです。
ではスモールスタートとして適切な業務にはどのようなものがあるでしょうか?多くの企業で財務部等の部署で管理している領域になりますが、銀行からの借入金を返済する業務については実は業種によってあまり差異がありません。借入金を返済するスケジュールは契約時点で日付/返済金額等が完全に固められています。利息部分については変動金利契約にすると多少の変動はしますが、大きなブレが発生することはさほど無いでしょう。固定金利契約であれば利息額含めて1円単位で完璧な予測をすることが可能です。
またリース契約で固定資産を使用する場合も、金利が上乗せされますが月額支払のリース料金はリース会社側で勝手に計算してくれます。あえて固定資産を購入するのではなく、リース契約を検討するのも資金繰りの観点でメリットが大いにあります。金利負担があったとしても管理工数を考えると実はコストパフォーマンスが高かったりします。
資金繰り業務のメインを担当するのは経理部門かもしれませんが、財務部門と連携をとれば上記のような資金繰り数値は簡単に入手できるかもしれません。また実現の難易度が高い例として、販売管理の分野をあげましたがサブスクリプションビジネスが大成功している会社であれば入金予測がスムーズにできるはずです。ここらへんもビジネスモデル等によって一概に言えないため自社を俯瞰してみることが大切です。やはり結果的には「全体最適」の視点も求められることは忘れないようにして下さい。
デリバティブを利用する
「デリバティブ」という言葉は聞いたことがある人が多いと思いますが、説明できる人は少ないかもしれません。主にデリバティブには「スワップ」「先物(さきもの)」「オプション」の3つの概念があります。個人が先物取引に手を出して大きな損失を出してしまった・・・みたいな高リスクなイメージが大きいかもしれませんが本来のデリバティブはリスク回避の手法として多くの企業で利用されています。
スワップは「交換する」という意味です。「“金利”スワップ」というと変動金利で契約した銀行借入を固定金利契約に変更(交換)することが一般的です。前章でお話した通り固定金利なら市場金利の高騰からリスク回避できますし、資金繰りの観点でみると1円レベルまで正確な将来予測ができます。
先物は将来発生する売買の金額をあらかじめ確定させておくデリバティブ取引です。例えば輸入業者の場合は円高が望ましいですよね。将来のある時点で1ドル=110円の為替レートで先物契約をしておけば、その時点で1ドル=130円(円安方向)になっていたとしても契約した為替レートで仕入をすることができます。
オプションは先物に似ていますが権利を破棄できるのが特徴です。先に出た1ドル=110円の例で説明します。この場合に契約した将来日付がおとずれた場合にさらに円高が進み1ドル=90円になっていたとします。この場合は1ドル=110円の権利を破棄して、1ドル=90円で仕入を行うことができます。選択権を強制行使しないといけないのが先物で、選択権を破棄できるのがオプションです。将来の仕入価格に変動はあるかもしれませんが、最低でも1ドル=110円で仕入を行えるという資金予測をたてられるのが、資金繰り業務に役立つのは明白です。
資金繰りの上手な会社はこのデリバティブを絶妙に駆使しているという印象を持っています。先物やオプションは業種によっては使用する場面が無いかもしれませんが、スワップあたりはどの企業でも利用できそうです。金利スワップをかけて、支払う利息額を固定化している企業はどの業種にも見られます。
ERP(Enterprise Resources Planning)は特効薬ではない
資金繰りを成功させるために、多くの人が注目することに「ERPシステムの導入」があります。これ自体が間違っているわけではありませんが、ERPの導入そのものが必ずしも特効薬になるわけでは無いことを認識しておきましょう。ERPは全体最適化の実現コンセプトを土台にして、部分最適化を実現できる多数のモジュールで構成されています。上手くERPの強みを把握して、取捨選択が出来れば資金繰り業務に応用ができるケースもあります。
ただし前回の記事でも触れた通りなのですがシステム会社とは「餅屋は餅屋」の世界で全ての業務を完全にカバーできるオールラウンドなものは実は多くありません。ERP導入だけでこれらの問題が完璧に解決されることはありません。
終わりに(次回展望等)
今回の記事では資金繰り業務のベストプラクティスにたどりつくための最初の一歩をどのように踏み出せばよいかといったテーマで、お話をさせて頂きました。資金繰りを正確に把握することは企業の生命線にあたります。全体最適目線でやらなければならないのは明白ですが、範囲が広すぎて最初から描いた理想のゴールに到達することはとても大変です。あえて部分最適目線でいくつかの成功事例を作ることを推奨いたします。
次回も資金繰りがテーマですが、今回とは切り口を変えてみます。学習と成長(人材育成等)という目線での記事を書こうと思っています。
クラージュUXのようなクラウド型の財務管理システムであれば記事で紹介させて頂いたような借入金の数値把握が簡単にできます。システム化しやすい部分からまずはスタートしてみましょう。