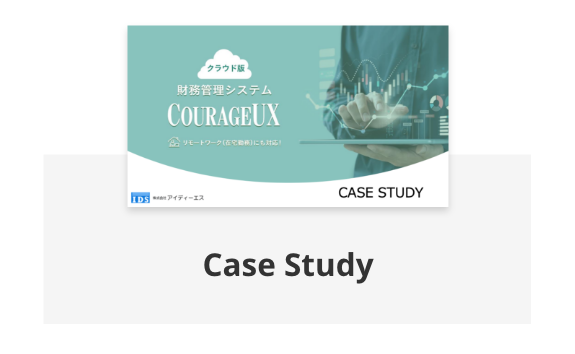webマガジン
Courage Lab
2023.10.26
COURAGEUX
資金調達
管理会計とは?実務に即して詳細に解説!
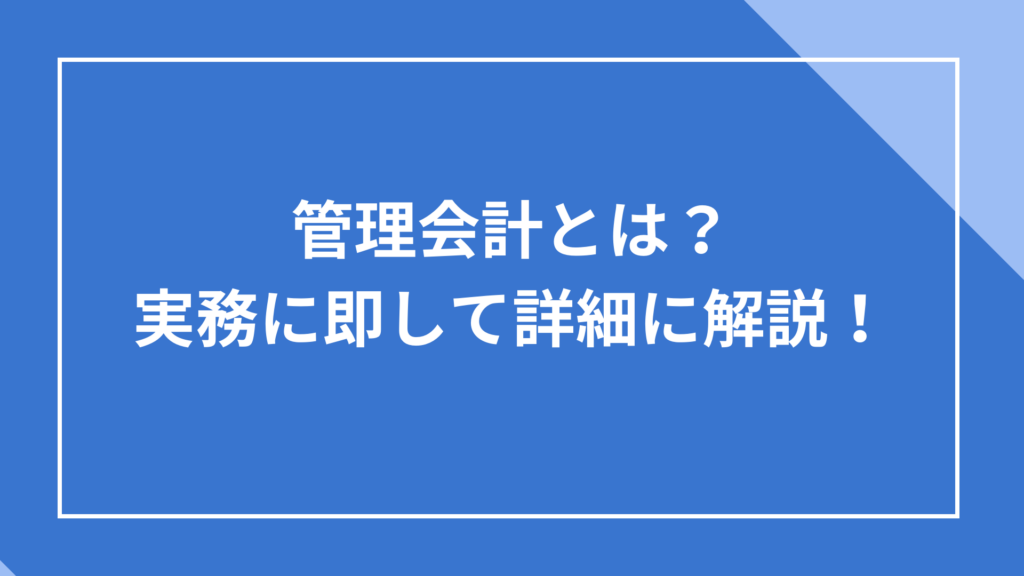
以前に管理会計というテーマで、説明を既にしております。そこでは主に財務会計や制度会計との違いや概要レベルのお話をさせて頂きました。今回は実務目線でもう少し具体的に説明していこうと思います。下記の記事にあげた以外にも、会計数値を用いて社内のステークホルダー向けに貢献する行動は全て管理会計と言えます。決められたルール(法律等)の中で勝負する財務会計に比べると、ずっと自由度が高いのが管理会計の世界です。管理会計は会社ごとに特色があるので、教科書だけで学ぶのは限界がある奥が深い学問です。実務レベルでは“ルールに縛られない”発想が必須です。
管理会計の主な業務(復習)
以前に管理会計では大きな4つの要素として、予実管理・原価管理・経営分析・資金繰りがあげられることを説明しました。復習しましょう。
①予実管理
事前に策定した予算と期間中の実際の業績を比較します。この比較により、計画通りの運営が行われているかを確認し、必要に応じて計画を修正したり、新しい対策を策定することができます。
②原価管理
製品やサービスの生産・提供にかかるコストを詳細に把握します。これにより、無駄を省いたり、コスト削減の方針を立てたりすることが可能となります。
③経営分析
企業の財務状況や業績、外部環境や市場の動向を総合的に分析します。この分析により、企業の強みや弱み、機会や脅威を明確にし、戦略や方針を練り直すことができます。
④資金繰り
短期・中期の資金の流れを予測し、適切な資金調達や使途の最適化を図ります。これにより、企業の健全な経営状態を保ちつつ、成長を支えることができます。
予実管理
ここでは予実管理(予算実績管理)について話してみたいと思います。
私も営業マンとして働いたことがありますが、営業マンとして働いた経験のある方は「予算」を必ず意識したことがあると思います。(せざるを得ないと思います!)営業マンを数年経験した人なら、予算を達成して上司から褒められて嬉しい思いをしたことがあるでしょう。モチベーションにダイレクトに直結するのが予算だと思いますが、未達だと胃が痛くなる予算、今期目標の達成が困難になると聞くのも嫌になるのが「予算」という言葉です。時には営業マンを苦しめてしまう予算ですが、ほとんどの会社でなくなることはないでしょう。
管理会計エリアの予算の話も実は財務会計と切り離せません。
会社ごとに中長期のビジョンが必ずあり、「100億くらいの売上を達成したい!5年後の経常利益額で昨年度の2倍にしたい!」・・・みたいな理想の損益計算書を未来予想図として描いているはずです。この未来予想図への道筋として予算があります。月次レベルで実績数値と予算を比較して、予算に届いていなければ軌道修正をする必要があります。
原価管理
営業マンだけに必要なわけではなく製造部門で働く人達も製造原価の目標数値(予算)を目指しているはずです。営業マンみたいに金額ベースでの目標では無く、行動レベルでKPI(重要業績評価指標)が定められている会社も多いはずです。この場合はKPIを通して間接的に予算達成のアクションを起こしているので「予算」という言葉の意識はしていないかも!?
原価管理で使用する原価計算は財務会計と管理会計が表裏一体の関係で付きまといます。
<財務会計の側面>
実際に製品を製造するのに掛かった原価がわからないと決算書が作成できません。これは外部ステークホルダー向けなので財務会計と言えるでしょう。
<管理会計の側面>
また完璧な原価を計算できても「A製品の売上目標1億円達成しました!でも製造原価が1.5億円掛かってました・・・」のような報告が1年終わってから上がってきたら、会社は潰れちゃいますよね。なので原価計算は一般的に必ず月次レベル以下の短期サイクルで行われます。先述したような望んだ利益が出ない状況になってときに、いち早く察知して軌道修正をかけてPDCAを回し続けて目標原価に近づけるためです。月次レベルの短期サイクルで行なわないと意思決定する材料が手に入りません。短期サイクルで社内管理用に利用するのは管理会計の側面が大きいです。
またユーザーの細かい要望にマッチできるように、時代の流れで多品種少量生産が求められる製造業の会社が増えてきているように思えます。同じラインで多くの製品を製造していると正直、水道光熱費等の原価はいくら分がこの製品のものって判断が難しいですよね?こうしたコストを「製造間接費」と呼びます。この間接的な費用をどうやって製品ごとに配賦するかも実は重要です。配賦方法で原価は変わってしまうのです・・・
製造間接費の占める割合が多い企業ではABC(エービーシー)が注目されています。ビジネスの世界でABCといえば、Aランク~Cランクにグループ分けするABC分析を頭に浮かべる人が多いと思います。でもここで言うABCは「Activity Based Costing(活動基準原価計算)」のことです。ABCはより客観的な間接費の配賦ができるメリットはありますが、そのために配賦の根拠になる材料を集めることができる社内整備が必要です。メリットだけを考えて安易に導入すると頓挫してしまう可能性が大です。間接費の増大が想定されている企業では入念な準備をしてこういった仕組みを構築すれば、かなり高度な管理会計が行えそうです。直接費が中心のビジネスならわかりやすいけど、間接費中心のビジネスになると原価という概念の捉え方も昔のままじゃ駄目かもしれません。
財務会計ソフトに求める管理会計機能
財務会計ソフトはクラウド型のパッケージ製品が充実している分野と言えますが、どのソフトにも管理会計に利用できる付属機能がふんだんに盛り込まれています。自社の管理会計の方向性を見極めて導入サービスを決めることが大切です。
予算管理一つをとっても、複数の予算を保持出来てるソフトもあります。どうしても挽回が難しい時には下方修正した予算に切り替える機能が役に立ちます。コロナ禍みたいな外的要因でどうしても当初予算の達成が困難になった企業は予算の下方修正を行わないといけない場面に遭遇するかもしれません。(そのままの予算じゃ従業員のモチベーションが下がってしまう・・・)
経営者が目標売上/利益の予測をたてるときに使用する損益分岐点が簡単に出力できるソフトもたくさんあります。しかし単純に勘定科目だけで変動費/固定費の切り分けが難しいケースが多いため、どういったロジックで分析かできるかを事前確認しましょう。実務レベルでは使えないこともあり得ます。
管理会計用フラグをつけた仕訳インプットができて、シミュレーション用の決算書を出力できるのは当たり前です。
ちょっとした実務場面から管理会計の事例を簡単に説明してみました。しかし冒頭にお話したように管理会計は法律等のルールに沿って行うものではありませんし、管理会計の専門書に書いていないような切り口で自社オリジナルの発想をふんだんに盛り込むことが大切な分野です。奥が深くて難しい・・・とは言えこの分野の学習の導入としては日商簿記検定の取得等が役に立ちます。受験する級によっては原価計算の体系的なロジックが勉強できたりします。そういった基礎がないと自社独自の発想が生まれないのも事実です。自社の管理会計レベルアップのためにまずは基礎から勉強を始めましょう。